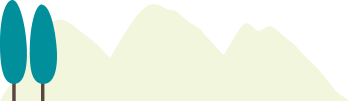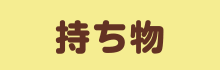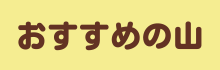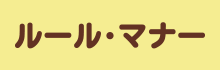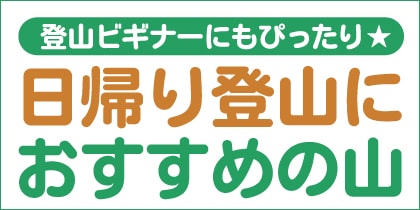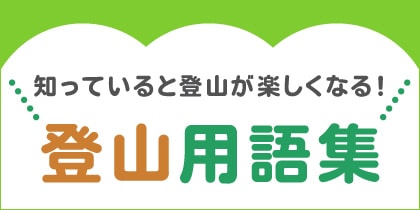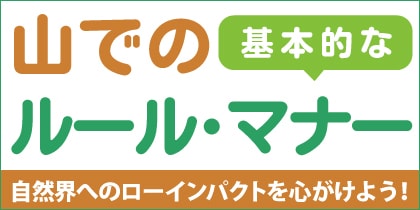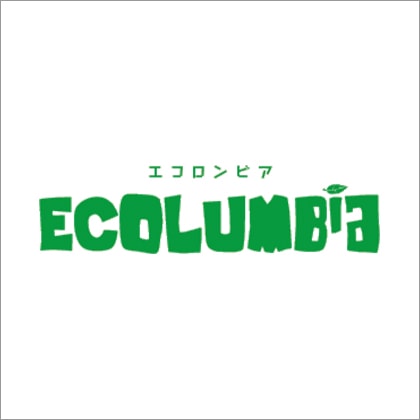| あ |
アイゼン |
雪上や氷の上を登る時に、滑り止めのために靴に付ける鋼鉄爪つき金具。 |
| アウター |
上着 |
| アプローチ |
自宅から登山口に至るまでの行程、方法。交通手段。 |
| 天蓋(雨蓋) |
トップロード式ザックの蓋。またはその蓋にあるポケット。 |
| アルピニズム |
より高く、より困難を求める、スポーツとしての登山。その技術や精神をいう。 |
| アンダーシャツ |
肌着。 |
| 鞍部(あんぶ) |
2つの峰をむすんだ稜線上の凹所。 |
| 一本立てる |
休憩、小休止のこと。 |
| インナーウエア |
下着と上着の間に着る衣類、中間着。 |
| ウェディングシューズ |
沢登りや川を渡るために設計された靴。濡れた岩の上でも登山靴よりも滑りにくい。 |
| 右岸(うがん)・左岸(さがん) |
谷や沢、川から下流方向を見た時、右側の岸を右岸、左側を左岸という。 |
| 馬の背 |
両側が切落ちた谷になっているような(狭い)尾根。 |
| エスケープ |
目的とするコースでアクシデントが発生して、目的を変えたりルートをかえたりすること。 |
| オイルコンパス |
内部に低粘度の油を満たした方位磁石。 |
| オーバーハング |
庇(ひさし)のように頭上に覆いかぶさるように突き出た岩壁。 |
| か |
カール |
氷河の浸食で半球状に削り取られた地形。 |
| 肩 |
山頂近くにある平坦地。 |
| 釜 |
渓谷にある円形の淵、火山の噴火口。 |
| 茅戸 |
茅が茂ったなだらかな尾根 |
| 空池(からいけ) |
長雨時以外は水のない池。 |
| カラビナ |
バネ式の開閉部がある金属製の輪。様々な登攀器具を接続するための器具。 |
| ガレ場 |
岩や石がごろごろしている箇所。その様を「ガレている」と言う。砂礫地の場合はザレ場と言う。 |
| 灌木(かんぼく) |
低い樹木のこと。 |
| ギア |
登山用具、またはその一式。 |
| キックステップ |
雪の斜面をつま先を蹴り込みながら登る方法。 |
| 切り通し |
尾根と交差する形で掘り下げて、道にしたところ。 |
| キレット |
山稜がV字型に深く切れこんで低くなっているところ。割れめ。 |
| クレバス |
氷河や雪渓上の深い割れめ。亀裂。 |
| ケルン |
石を積み上げて道標の代わりとしてある物。 |
| 原生林 |
人間が手を加えていない自然のままの森林。 |
| GORE-TEX(ゴア・テックス) |
多孔質構造をもつふっ素系樹脂の極薄フィルム。水は通さず、水蒸気は通すので、雨具に利用すると蒸れない。さまざまな登山用具に使われている。 |
| コース |
登山道のこと。定められた進路。 |
| ゴーロ |
岩や石がごろごろしている沢。 |
| コッフェル |
組み合わせ式の鍋。アルミやステンレス製の大鍋・小鍋・フライパン・皿などがワンセットになったもの。 |
| コブ |
尾根にある小さな隆起、突起。 |
| ゴルジェ |
渓谷の両岩壁が細く狭まった箇所。 |
| こんにちは |
登山者同士が交わす挨拶。 |
| さ |
ザイル |
登攀用ロープ。 |
| 山行(さんこう) |
登山をしに山へ行くこと。 |
| 山座同定 |
山頂などから見える山々の山名を確定すること。 |
| 三点支持 |
岩場を登るときの基本の動作。 |
| シェルパ |
ヒマラヤなどの山案内人。荷運び人。 |
| シーム |
縫い目。そこから雨水が漏れないようにする防水加工をシームリング加工という。 |
| シャリばて |
空腹でパワーが出ないこと。シャリは米飯の意。 |
| シャワークライミング |
滝の飛沫を浴びながら登ること。 |
| ジャンクションピーク |
大きな山稜がいくつか交わった地点にあるピーク(山頂)。 |
| シュラフ |
袋型になった寝具(ふとん)。 |
| 小休止 |
短い休憩。 |
| 背負子(しょいこ) |
荷物を背負うためのフレーム。 |
| 森林限界 |
高山の森林成育の限界。 |
| スタッフバッグ |
小物品を収納するための袋。巾着型のナイロン製の袋。 |
| スラブ |
手足をかける所がない、凸凹の少ない一枚岩。 |
| 雪渓 |
谷間等にある万年雪。 |
| 双耳峰 |
動物の耳のように、2つのピークが並んでそびえている山頂。 |
| 装備 |
ある目的のために付属品などを取り付けること。登山に必要な道具・用品類のこと。 |
| 遡行 |
谷や沢を上流へ向かってさか登ること。沢登り。 |
| た |
ダイヤモンドダスト |
極寒のときに空気中の水分が氷結し、太陽に反射してキラキラ光りながら降る現象。 |
| 探勝 |
名勝探訪の意。自然の美しい地を訪ねて歩くこと。 |
| 池とう |
高山の湿原に点在する小さな池。 |
| 出合 |
2つの川(谷・沢)が合流する地点。 |
| 低体温症 |
体が極度に冷やされることにより体温が下がり、筋肉や脳に異常が起こる症状。 |
| デポ |
荷物を一時置いておくこと。預けること。 |
| 徒渉 |
川や沢(水の中)を歩いて渡ること。 |
| トラバース |
横断。頂上へ行かずに山腹を横ぎること。 |
| ドリネ |
摺り鉢状の窪地(谷)。 |
| トレイル |
元々は山道の意。行程。人が歩いて道のようになったところ。 |
| トレッキング |
比較的長期間の徒歩旅行。健康やレクリエーションのために山歩きをすること。 |
| トレッキングシューズ |
本格的登山靴に対して、軽量な登山靴。 |
| トレッキングポール |
登山用の杖。 |
| な |
鉈目(なため) |
樹木に刃物で切り目を入れて道標の代わりにしたもの。 |
| 滑(ナメ) |
なめらかな岩の上を水が滑らかに流れているところ。 |
| 難路 |
通過することが難しい登山道。 |
| 日本三名山 |
名高い日本の三座の山。一般に富士山・立山・白山。 |
| ぬた場 |
猪等の動物が体を冷やしたり、ノミを取るために泥浴びする小さな湿地。 |
| は |
パーティ |
登山時のグループ。 |
| ハイドレーションシステム |
水筒の本体がザック内にあって、ホースが出ており、ザックを背負ったままで水を飲むことができる仕組み。 |
| パウダースノー |
湿り気が無く、粉末のようにさらさらしている雪。 |
| 幕営(ばくえい) |
テントを張ること。キャンプをすること。 |
| 撥水加工 |
衣服などを、水滴をはじくように加工すること。 |
| パッキング |
ザックへ物を詰めること。 |
| 飯盒 |
焚き火で飯を炊くための携帯用の釜(器)。 |
| ハンディGPS |
小型のGPS装置。 |
| ピーク |
頂上のこと。山のてっぺん。 |
| ピッケル |
氷雪地帯を登攀するためのつるはし。滑落停止、足場切り、手がかり、確保支点などに使う。 |
| ピッチ |
同じことを繰り返すとき、その速度や回数。 |
| ヒュッテ |
山小屋。 |
| ファーストエイド |
応急手当。救急処置。 |
| 伏流(ふくりゅう) |
沢や川の流れがいったん川底にかくれて見えなくなること。 |
| ブッシュ |
藪。潅木(かんぼく)地帯。 |
| ブロッケン現象 |
高所で前方に霧や雲がある時、前方に光輪ができ、その中に自分自身の影が映る現象。 |
| 分岐点 |
尾根や登山道が2つ(以上)に別れている地点。 |
| へつり |
沢登りで、水際の岸壁をへばりつくようにして横に進むこと。 |
| ホールド |
岩登りをする際の、手がかりのこと。足がかりはスタンス。 |
| 歩荷 |
山小屋などへ荷物を運ぶ人。 |
| ホワイトアウト |
濃霧や吹雪のために視界が真っ白くなり、何も見えなくなること。 |
| ま |
マーキング |
印を付けること。 |
| 巻く |
難所や滝、山頂等を避けて迂回して登ること。 |
| マップメジャー |
地図上の距離を測る道具。 |
| や |
藪漕ぎ |
草や木をかき分けて進むこと。 |
| 山ガール |
登山を楽しむ女性。 |
| 山開き |
登山で一般の人が登拝できる期間の始まり。一般に7月1日あたり。 |
| ら |
落石 |
石が転がり落ちること。 |
| ラッセル |
深い雪を踏みつけて、道をひらきながら進むこと。 |
| ランタン |
ガソリン、石油、ガスを燃料とした燈火。 |
| 稜線 |
高い山の背にあたる、峰から峰へ続く線のこと。 |
| リングワンデルング |
濃霧や吹雪に巻かれたときに、方向を見失って周回運動(元の場所に戻ってくること)をすること。 |
| 林道 |
主に林業用に作られた車道。 |
| ルートファインディング |
道や登攀コースを見分け見つけること。 |
| レイヤード |
重ね着。気温や運動量の変化に応じて服を重ね着したり脱いだりして、体温を合理的に維持すること。 |
| レスキュー |
救援、人命救助。遭難救助隊。遭難した人を助けること。 |
| わ |
ワカン |
雪の上を歩くための輪状の歩行具。「輪かんじき」の略。 |
| ワンダーフォーゲル |
史跡・旧跡等を訪ね、自然を観察し、各地の風俗・習慣を学ぶ、20世紀初頭にドイツで起こった青年運動。 |